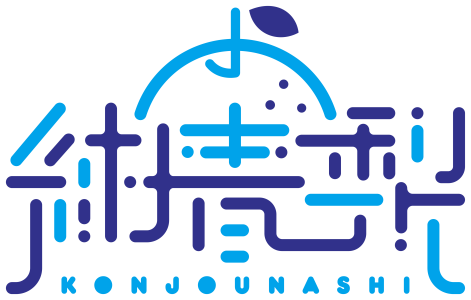「青道高校出身!ポジションは投手希望です!」
お前が投手なのはみんな知ってるわ!甲子園優勝校のエースめ!と知らない先輩に野次られた。大学野球一日目、三年生の集団の中でクリス先輩がクスクスと笑っていた。目が合うとヒラヒラと手を振ってくれる。
「そこにいらっしゃいます滝川・クリス・優先輩とバッテリーを組むために来ました!よろしくお願いしやす!」
そうかクリスも青道か、と何人かの先輩たちが話している。投手陣からはもう正捕手指名か!と声がかかる。
クリス先輩が正捕手!とそれだけが嬉しくなってしまって元気にハイ!と返事をすると笑いが起きた。嫌な感じはしない。いいチームだ。
一通り新入生の自己紹介が終わると苦笑しながらクリス先輩が俺の方へ近付いてきてくれた。
「…本当に来たんだな。推薦とは言え、よく合格したな」
「カネマールの方へ足を向けて眠れません!」
「よく言うよ!もっと俺に感謝しろよ!…クリス先輩、またこの馬鹿とお世話になります」
「金丸がいれば沢村の勉強は安心だな」
金丸が少し怒りながら寄ってきた。頭を下げるとクリス先輩はさらに楽しそうな顔をする。
「苦労をかけるな、金丸」
「本当ですよ、コイツ全部俺と同じ授業取るんですよ」
「学部も一緒か、頼もしいな」
クスクスと本当に楽しそうにクリス先輩が笑っていて嬉しくなってしまう。尻尾出てるぞ、と金丸に指摘されて尻を抑えると冗談だよ、と呆れられた。
「練習の後、飯でも行くか?」
「師匠とお食事ですか喜んで!」
「俺はお邪魔だと思うので遠慮しときます」
驚いて金丸の方を向くと肘で小突かれた。御幸先輩にもバレていたので散々相談はしていたのだが、勉強会に紛れて金丸にももう聞き飽きた!と言われるほど相談していたのだから気を遣ってくれたのだろうがあまりに突然で混乱する。
「そろそろ素直になった方がいいと思いますよ、二人とも」
え?とクリス先輩を見れば同じように困惑した顔のクリス先輩と目があってしまいもう一度金丸を見る。
「俺も御幸先輩もいい加減板挟みに疲れました」
金丸の爆弾発言はあったが、練習中は野球に集中してしまうのでクリス先輩とも以前と変わらず接することができていたと思う。クリス先輩も練習を疎かにする人ではないので不自然な事もなかった、と思う。
結局、久しぶりだし食事はしようと一緒に学校を出たところまでは良かったが、そこからは途端にギクシャクしてしまい、クリス先輩がよく行っていると言う大学近くの定食屋へ連れて来てもらった。
「…沢村は、寮じゃないのか?」
「は、はい。卒業後プロになるなら今を逃すとまたしばらく一人暮らしのチャンスがなくなるから、と両親が…」
家族は、早く番を見つけるために俺に一人暮らしをさせたかったのだと思う。俺の魂現が断絶種であるオオカミだからだ。何故か沢村家は絶滅したはずのニホンオオカミの魂現を細々とつないできた。
原因はわからないが代々長子は必ずオオカミなのだ。番が軽種の犬神人だろうが猫又だろうが、必ず一人目の子供はオオカミが生まれて、それがずっと続いて来たけれど、とうとう国内に他のオオカミの血筋がなくなってからは変え魂をするようになった。
生まれた時にそうさせるせいで馬鹿な俺ですら無意識でもずっと変え魂が出来てしまっている。本当の恋をして好きな人と結ばれたら解ける呪いのようなものだと祖父ちゃんは言っていた。
「…早く番を作ってしまえ、と?」
「…まあたぶんそうでしょう」
「お前は、変え魂しているよな?」
へ?とクリス先輩の突然の言葉に変な声が出てしまった。ほんのり頬を染めたクリス先輩は綺麗で可愛くて、ほんの少しいつもの森の匂いに混じって甘い良い匂いがする。
「…俺も、本当はゴールデンレトリバーなんかじゃないんだ」
「先輩、俺ん家来ませんか」
自然と口に出ていた俺の言葉に、クリス先輩は赤い顔で頷いた。
毎食三杯の高校時代の食事のせいですっかり大きくなった胃は大学生向けの定食屋の多めの食事も平らげるのには苦もない。ご馳走様でした、と手を合わせ、支払いを済ませて店を出たところで思い切ってクリス先輩の手を握った。
一瞬強張った手は、ゆっくり握り返してくれて、金丸の言葉が冗談ではなかったのだと染み入ってきた。
「…金丸と御幸には、悪い事をしたな…」
「…まさか、師匠も同じ二人に相談してたなんて…御幸、先輩は影で笑ってたりしたんじゃないですか?!」
「そんなことは、きっとしないだろ」
クスクスとクリス先輩が笑っている。甘い匂いが強くなる。これが蘭の匂いなのだろうか。
「クリス先輩は結構御幸先輩に甘いですよね」
「…俺にとっては可愛い後輩だからな」
「可愛いですか?あの男が?」
「シニアの頃は御幸も小さくて可愛かったよ。今だってたまに連絡するとすごく嬉しそうに返事が着て、可愛いなと思う」
楽しそうにクリス先輩が笑う。俺も楽しくなってたくさんくだらない話をした。そのどれもにクリス先輩が笑ってくれる。
大学に近い定食屋からは大学の近くに借りた俺の部屋はそんな風に話していればすぐの距離だった。
お邪魔します、とクリス先輩が玄関を通り抜けて俺の部屋へ入ってくるだけでどこか感動を覚えた。クリス先輩が!俺の部屋にいる!御幸先輩に自慢したらあの人はどんな顔をするだろう。
何もないですが、ととりあえずお茶を出す。近所のスーパーで安売りしていたペットボトルのお茶をガラスのコップに移しただけだが、クリス先輩の前にあるだけで少し高そうに見える。
「そう言えば、運命の相手は蘭の匂いがするんだってお前は言っていたな」
ソワソワウロウロとしていた俺に、クリス先輩がお前は座らないのか?と笑うのでそそくさとローテーブルの向かいに座った。今日はたくさん笑ってくれている。出会ったばかりの頃には考えられなかった。
「…初めてこの匂いがお前からするんだと気付いた時は、俺は絶望したよ」
俺の方を見て笑っていたクリス先輩が三年前を思い出すように俺から視線を外してまだ白い壁を見た。まるで壁のその向こうまで見えてるみたいだ。
言葉とは裏腹にクリス先輩の顔はまだ微笑んでいる。
「あぁ何で今なんだって、せめてもっと早く、御幸より先に出逢いたかったと思った」
「…へ?えっどういう事ですか?」
「だってお前は投手だから、正捕手の御幸の方がきっと魅力的に写るだろうな、と思ったんだ」
馬鹿だろう?とクリス先輩が笑う。
「実際、お前は御幸の後ろばかり追って、最初は俺の事が苦手だっただろう?」
「…あの頃は、俺が今よりもっと未熟者だったのが悪いんです。師匠は何も…!」
人差し指で唇を押さえられてむぐ、と黙らされてしまった。
「嫉妬したんだ。俺にはもう一年もないのに、御幸はまだ一年以上一緒に居られる、バッテリーにもなれるんだって、だからたぶん、もしかしたら他の投手よりもお前には辛く当たってしまったかもしれない」
クリス先輩が微笑みながら俺の左手を大事そうに撫でる。そんな顔をされたら、嬉しくて舞い上がってしまいそうだ。
「…初めて会った時からずっと、お前から蘭の匂いがしていた」
「クリス先輩、俺も…」
「俺もお前と同じオオカミだ」
真っ直ぐ、クリス先輩が俺の目を見た。先輩の瞳が金色に輝いたように見えるとぶわりとあの森の匂いに包まれたように感じる。甘い優しい匂いも強くなる。
「俺は外来種だけど、お前はこの国の断絶種だろう?だからきっと、お前の感じたいい匂いは数少ない同種を感じただけの勘違いだ」
「クリス、先輩…?」
「きっと、勘違いだから、ただのバッテリーとして、お前の捕手として、大学の間だけでいいから俺がそばにいる事を許してくれ」
「でも、おれもっ」
「いいや、お前のは勘違いだよ。降谷が御幸に感じていたのときっと同じだ」
俺が呆然としている間にお茶を飲み干したクリス先輩は帰って行ってしまった。また明日、と笑って、一度も振り返る事なく俺の部屋から出て行ってしまった。
何をどう声に出せば良かったのだろう。カラカラに渇いた喉が、掠れた泣き言の一つも出させてくれなかった。
帰っていく先輩は本当に笑っていただろうか。どうして、勘違いだと言うのだ。
倉持先輩と御幸先輩達のようには俺があなたを見ていないと三年前に言ったからだろうか?あなたの匂いを蘭の匂いだとあの時言えなかったからだろうか?
ぎゅうっと胸が締め付けられる。あなたに突き放されてこんなにも辛いのに、どうしてこれが勘違いだと決めてしまうんだ。叫びたいのに渇いた喉は引きつって声が出ない。
遠くで悲しげな犬の遠吠えが聞こえた気がした。
「御幸先輩!」
『金丸から聞いたぞー、クリス先輩と二人で飯行ったんだろ。どうだった?』
「振られました!!」
は?と電話越しに驚いたような御幸先輩の声がした。
すぐに一人で部屋にいるのが耐えられなくなって、散々お世話になった先輩の電話番号をタップした。繋がらなかったら諦めて寝てしまおうと思ったのに楽しそうな声が返ってきて正直にぶちまける。
『お前、クリス先輩に何したんだよ!』
「まだ手しか繋いでないっす!」
ぐす、と鼻を啜ってしまうと電話の向こうから、お前泣いてんの?大丈夫か?と珍しく心配そうな御幸先輩の声が聞こえた。
「だって、だっておれ、何も言わせてもらえなくて!」
『あーもー、お前倉持の家知ってる?今からおいで。家主は説得しとくから』
「先輩たちのじゃましたくないっすー」
『こんな電話かけてきといて何言ってんだよ、放って置けるわけないだろ。いいからおいで』
優しい声がする。俺はあんなに御幸先輩のことを疑ってしまったのに、心配してくれている。
『あ、家主の説得のためにケチャップ買ってきて』
ケチャップ?と聞き返すとまあまあいいから、と言って電話は切れた。
一度だけお邪魔したことのある倉持先輩の部屋の呼び鈴を鳴らすとすぐに扉が開いた。扉を開いた倉持先輩がギョッとした顔をしていた。
「おま、泣き過ぎだろ」
「もっぢぜんばい〜」
「おう、上がれ。御幸から話は聞いてるから怒りゃしねえよ」
ぐしゃぐしゃと頭を撫でられた。元ヤンだから顔は怖いし基本的に手つきは乱暴だが優しい先輩なのは寮で同室だったからよく知っている。
部屋に通されると、うわーべちゃべちゃだな、と言いながら御幸先輩がホットタオルをくれた。代わりに俺は途中スーパーに寄って買ってきたケチャップを渡す。あれからずっと涙が止まらなくてそのまま店に入って真っ直ぐケチャップだけを手にレジまで行ったので店員さんにはビビられたがそんなことはもう今の俺にはどうでも良かった。
ちょっと待ってな、お前も夜食軽くなら食えるだろ?と倉持先輩よりは優しく頭を撫でて、俺が頷いたのを確認した御幸先輩は小さなキッチンへ向かった。
「感情表現の大袈裟な奴だと思っちゃいたけど、今日は桁違いだな、お前」
いつになく優しい二人にボロボロと溢れる涙が止まらない。何で、どうして、と心はまだそれだけを叫んでいるみたいだ。
「ほら、水分とっとけ」
倉持先輩がよく冷えたスポーツドリンクのペットボトルを一本くれた。ゴクゴクと飲み込むとそのまま喉に染み入る気がした。
「なんで、そんなに、優しいんですか」
「一応、お前も可愛い後輩だからな」
また倉持先輩が乱暴に俺の頭を撫でた。御幸先輩ともクリス先輩とも違うけれど、いつも乱暴な仕草に隠して俺を気にしてくれていた。
「まあ春市ほど可愛かねーけど」
「何でですか!確かに春っちは顔は可愛いですけど辛辣な男ですよ!五号室の絆はどこいったんですか!」
「お前うるせーからよー、浅田の次ぐらいには可愛いと思ってるよ」
「浅田は可愛い後輩っすね!わかります!」
「お、ちょっと元気になったな、沢村」
おまたせー、と御幸先輩が皿を持って戻ってきた。皿には大きなオムライスが乗っていた。
「でかいのは倉持な。沢村は夕飯、クリス先輩と食べたんだろ?」
クリス先輩の名前にまた止まりかけた涙が出そうになるとあーあー、と御幸先輩が呆れたような声を出しながら俺が手に持ったままだったタオルで顔を拭ってくれる。まるで自分が小さな子どもになったような気分だ。
倉持先輩の前に置かれたものより二回りぐらい小さいオムライスが俺の前にも置かれた。俺の顔を拭うと、もう一度キッチンに戻った御幸先輩がもう一つ小さめのオムライスとケチャップを持って戻って来た。
「食べながら話聞いてやるから、そろそろ泣き止めよー、沢村」
「だって、御幸先輩。クリス先輩が、俺の気持ちは勘違いだって。こんなに苦しいのに、違うんだって」
そっか悲しいな、と御幸先輩が俺の背中を撫でる。
「この国のオオカミは断絶種だから、同種の匂いを勘違いしてるだけだって言うんです」
「まあ俺も、それはちょっとあるんじゃねーかとは思うよ。ちょっとだけな」
「なんで御幸先輩までそんなこと言うんすか!じゃあ御幸先輩も他の天狗に会ったら倉持先輩ぐらい良い匂い感じるんすか?ないでしょう?そんなはずないのに!」
落ち着けって、と御幸先輩が優しく背中を撫でてくれる。何で、どうして、俺のことわかってくれないんだ、と苦しくなる。マウンドとキャッチャーボックスに居る時は、言葉がなくてもボール一つで通じるのに、どうして、とまたボロボロと俺が泣くと、まあ聞けって、と御幸先輩が苦笑しながら俺の頭を優しくその胸に抱き込んだ。
「俺は他の天狗に会ったことないからわかんないけど、でも同種に感じる匂いはきっと倉持ほど甘くて優しい匂いはしないと思う。同種の匂いもきっかけにはなったって本物にはならないよ」
倉持先輩がきっと怒るのに、優しい手に抗えなくて甘えるように御幸先輩に縋り付いてしまうと、俺を抱き締める二本の腕とは違う手が俺の頭を撫でた。
「いくら大好きな人でもそんなこと言われたら泣きたくなっちゃうよなぁ、沢村」
優しい御幸先輩の声がする。御幸先輩だって、一番尊敬しているクリス先輩をきっと本当は否定したくないと思う。それでも、俺に寄り添ってくれた。
もう何も言葉は出なかった。心が苦しい。一番知って欲しかった人に否定されてしまった心が、軋む。せめて、否定するなら俺の話だって一度でいいからちゃんと最後まで聞いて受け止めてから否定して欲しかった。
「泣いとけ泣いとけ、そんで明日酷い顔になって心配させてやれ」
倉持先輩の独特な笑い声がする。御幸先輩に対して独占欲の塊みたいな人が、俺が御幸先輩に縋り付いても怒っていない。
「それでもお前の本気が伝わらねえなら、幾ら先輩だって俺がぶん殴って目覚まさせてやるよ」
乱暴者だけど優しい先輩の言葉が、軋んだ心を撫でてくれた気がした。
「沢村ー、そろそろ起きろよ。朝飯作ったから食ってけ」
御幸先輩の声に目を擦ると、あーもういっかそれ以上酷い顔にはなりっこないな、と優しい声が笑っている。昨日オムライスが置かれていたテーブルの横に敷かれた布団に寝ていたらしい。
「みゆき、せんぱ…?」
「お前昨日泣きながら寝ちゃったんだよ、ここ倉持の家」
「くらもちせんぱい…」
「倉持はまだ寝てるけどお前も今日練習だろ」
顔洗っておいで、とテーブルにサラダと目玉焼き、小さめのウィンナーが数個とトーストが二枚乗った皿を御幸先輩が並べている。旨そうな匂いにぐぅ、と腹が鳴った。
「洗面台の下に新しい歯ブラシあるから」
「…御幸先輩の家みたいっすね」
「まだ数回しか来てないけどな」
優しい顔で御幸先輩がベッドを見つめている。つられるようにそちらを見ればスヤスヤと大きな猫科の猛獣が眠っていた。寮で同じ部屋で生活していたのに一度も見たことがなかった倉持先輩の魂現のままの姿だ。
「かっこいいだろ、俺の雄」
「…元気になったら惚気どんだけでも聞くんで、今は勘弁してください…」
「俺はそろそろお前の惚気が聞けると思ってたよ」
ぐりぐりと御幸先輩が俺の頭を撫でる。
「お前酷い顔してるからさ、今日はそれでめちゃめちゃ心配させて、そんでまた明日からはお前らしくグイグイいきな。大丈夫だよ、クリス先輩はお前のその勢いに一度救われたんだから」
わかんなくなったら金丸にも聞きな、と御幸先輩が笑う。俺と金丸は板挟み仲間だからな、といつものニヤニヤとした優しくない笑顔に思わず笑ってしまうと、ほら早く顔洗って来い、と背中を押された。
「御幸、俺の飯は?」
「ちゃんとあるって、お前も顔洗ってこい」
顔を洗って歯を磨くと少しスッキリした。部屋へ戻れば倉持先輩が朝食の匂いにつられて起きたようだった。目を擦りながら俺と入れ替わりに洗面台へ倉持先輩が向かっていた。
「沢村、コーヒー飲める?」
「飲めますよ!」
「へー、倉持より大人じゃん」
「俺だって飲めるっつーの!」
「倉持のはコーヒーじゃなくてほぼ牛乳だろ」
ぐぬぬ、と顔を洗って戻ってきたいつもの調子に目が覚めた倉持先輩が唸る。この顔で子供舌なところをきっと御幸先輩は可愛いと思ってて、そしてそこが好きな癖に、好きだから弄ってしまうのだ。
「あんだけベソ書いてた癖にもう元気じゃねーか、沢村」
「あっ!俺のウィンナー!!」
「コラコラ、ちゃんとお前のもあるんだから」
「…オムライス、食い損ねた…」
俺が肩を落としていると御幸が笑っている。
「ほら、大サービスで弁当作ってやったから、持って行きな」
部室で俺の顔を見た金丸は、何も言わずにいつも通りでいてくれた。きっと御幸先輩が連絡してくれたのだろう。なんだかんだ言いながらあの人は未だに投手に甘い。
他の部員にはギョッとされるほど俺は酷く泣いた後だとわかる顔をしていた。普段通りの金丸が隣にいたので他の部員は特に何かを言ってくることはなかったけれど、クリス先輩は少しだけ困った顔をしただけだった。心配もして貰えないのか、このぐらいは想定の範囲内であんなことを俺に言ったのだろうか。
ぎゅう、と心がまた軋んだ。無意識に胸の辺りを押さえていると、大丈夫だよ、と笑う御幸先輩の声を思い出す。
「勘違いなんかじゃないですから」
クリス先輩の目をまっすぐ見て俺がそう言うと、クリス先輩は驚いた顔をしていた。金丸が俺の背中をポンと叩いてその場を離れる。
「俺は諦めません、あなたの事。信じて貰えるように努力します。バッテリーだけじゃなくて、俺を認めて貰えるように」
だから覚悟してください、と宣言すると近くにいた別の先輩に熱烈だな、と言われたクリス先輩が真っ赤になった。ぶわりと甘い匂いが広がって、俺もつられて赤くなってしまうと、クリス先輩はしまった!と言う顔をして走り去った。
「…すげーな、沢村」
「へ?え??な、何ですか?え?」
「あんなに焦ってるクリス、初めて見たぞ」
「…俺も初めて見ました…」
練習は俺の顔以外は何事もなく進んでいった。野球をしている間はクリス先輩に何を言われても近くにいても胸が苦しくはならなかった。
昼の休憩で、弁当を開けて俺は一旦そのままその蓋をしめた。隣で金丸がうわー、と頭を抱えているので見間違いではなかったらしい。
意を決してもう一度そっと開けると黄色い卵の上にケチャップで大きくハートが書かれていた。ちょっと歪んでいるのがなんとも野球以外はからきしの御幸先輩らしい。料理は得意なのにそこはダメなのか、とも思う。
「お、沢村は一年のくせに愛妻弁当持参か!生意気な!」
倉持先輩ほどではないがそこそこ容赦のないヘッドロックを食らう。まだ先輩たちの名前は覚え切れていないがこの雰囲気は少し懐かしくなる。
「違います!違いますって!昨日ちょっと色々あって、泊めてもらった高校の先輩の悪戯です!」
「…御幸先輩、結構怒ってんな、これ」
歪んだハートマークを見ながら金丸が不穏なことを言う。
「え、マジで?!どうしよう!もっち先輩に殺される!」
「いや、怒ってんのはお前にじゃねーだろ」
みゆき、と言う名前の響きにやっぱ女じゃねーか!とヘッドロックがきつくなる。ギブギブ!とタップすればすぐに離してくれるところは倉持先輩よりよほど良心的だ。
金丸に肘で小突かれて正面に座ったクリス先輩を見ると呆然と固まっていた。
「…クリス、先輩?」
「御幸と、昨日会ったのか」
「倉持先輩の家に呼び出されまして…もちろん倉持先輩もいました、よ?」
「いや、いいんだ。俺は…」
何で、どうして、アンタがそんなに傷付いた顔をするのだ。
そう言ってやりたいけど周りに人がたくさんいて、口に出すことは出来なかった。横を伺えば金丸は少し呆れた顔をしている。そうだよな、呆れたってイイんだよな、俺も。
「御幸先輩、性格は悪いけど顔と料理の腕と捕手としては最高ですよね」
御幸先輩を真似するつもりでニヤリと笑うとクリス先輩が苦笑した。あんなに酷いことを言われたのに、苦笑でもクリス先輩が笑ってくれると嬉しくなってしまう。
「青道出身の捕手でみゆきって、…御幸一也か!」
「アイツ、ドラフト一位指名でイケメンでさらに料理まで出来んのか!」
周りにいた先輩たちが騒ぎ出す。流石野球馬鹿の集団である。
「そういや高卒一年目からずっと一軍に居たのが一昨日になって突然登録抹消されたって、なんかあったのか聞いたか?沢村」
「えっそんなことになってたんすか?俺全然知らなくて聴いてないっす」
言われてみればそうだ。もうプロ野球もシーズンが始まっているのに、まだ球団の寮にいるはずの御幸先輩が倉持先輩の家にいた。自分の事だけで精一杯で理由なんて考える余裕がなかった。
「怪我とかは、なさそうでしたけど…倉持先輩も何も言ってなかったし…」
「倉持先輩が何も言ってないなら大丈夫だろ」
「もっち先輩、御幸に対して過保護過ぎるもんな」
「御幸『先輩』だ、ばかむら!」
金丸の言葉に納得しながらようやく昨晩食べ損ねたオムライスを口に運んでいると、倉持って青道の御幸世代の副主将だっけ?と先輩たちが話す声が聞こえる。A大だっけ?俺は倉持もプロ行くと思ってたー、などと話している様子になんだか誇らしくなる。御幸のオムライスは冷めても美味かった。そうだ、俺の自慢の先輩たちだ。
「すげー先輩たちと野球してたんだなぁ、お前ら。いやお前らも甲子園優勝してんだからすげーんだよな」
「俺らも舐められねえように頑張らねえと」
すげえすげえと言いながらもそこで自分たちももっと、と思える先輩たちのいるチームに自分が加われたことが嬉しいと思う。
「つーか、沢村もプロ行くんじゃねえかと思ってたよ俺」
「俺は、降谷みたいに力で捻じ伏せるタイプじゃないのでもっと勉強してからでも遅くないと思ったんす!」
「青道は投手が充実してたもんなー」
この人たちは本当に野球が好きなのだとヒシヒシと感じる。練習中だってそれなりにきついはずなのに楽しそうだと思って、クリス先輩が居たのは大きいがそう言うところもいいな、と思ってこの大学に決めたのだ。
「あとはどうしてもクリス先輩とバッテリーを組みたかったので!」
「御幸と組んでた癖にそんなこと言われちゃクリスも可愛がるわそりゃ」
「御幸なんか師匠に比べたらまだまだ全然っすよ!」
「だーかーらー、御幸『先輩』な!」
ゴツン、と金丸に拳骨を落とされた。お前ら仲良いなぁと先輩たちが笑う。クリス先輩も今度こそいつも通り優しく笑っていた。
御幸先輩なんかあったんすか、とその夜、今更ながら倉持先輩へメッセージを送ると、お前は気にするなってよ、とすぐに返信があった。たぶんまだ御幸先輩は倉持先輩の部屋にいるのだろう。任せろ、と胸を張る御幸先輩の球団のマスコットのスタンプが押されてはそれ以上は踏み込めなかった。
オムライス美味しかったです!と返信してアプリを閉じる。
倉持先輩と御幸先輩は喧嘩ばかりしていたが、それでもちゃんとお互いに支え合ってた。青道野球部の中ではあの二人の関係に憧れていた斑類も多い。
グラウンドへ出れば主将と副主将としてきっちり線を引いて、ポジションは違ってもお互いを鼓舞するようなプレーをしていた二人だった。寮に戻れば異様に距離が近いことはたまにあったが、他人の目があるところではきちんと節度を守っていた。
あんな関係に、なりたかった。きっとなれると信じていた。
一度心を開いてくれてからはずっとクリス先輩はまるで倉持先輩が御幸先輩にするように、俺に優しく笑いかけて楽しそうにしてくれていたから、あんなことを言われるなんて思ってもみなかった。
御幸先輩だって、俺の惚気が聞けると思っていたと言ったのだ。金丸も今日、俺が御幸先輩と会っていたことに何か言おうとしてやめたクリス先輩に呆れていた。きっと俺だけの勘違いではなかったはずだ。
師匠として慕っていた。いやきっと、初めて出会った時、あまりにどんよりとしていたクリス先輩の目にばかり意識が向いてしまって気付かなかっただけだ。その後も未熟な自分が勘違いをしていて、御幸先輩を怒らせて、そうしてやっとクリス先輩の凄さがわかって、ついて行くのに必死で、そうしてようやくクリス先輩が笑ってくれたときに、ぶわりといつもしていた森の匂いの中に花が咲いたと思った。
あの瞬間が、俺にとっての運命の始まりだ。きっかけは森の匂い。まだ花は咲いていなかったけど良い匂いだと思った。それはきっと御幸先輩が言っていたきっかけに過ぎない。
ほら、違うじゃないか、と心が叫ぶ。何で、勘違いだと俺を諦めようとするんだ!
俺の運命はあなたなのに!それ以外なんていらないのに!