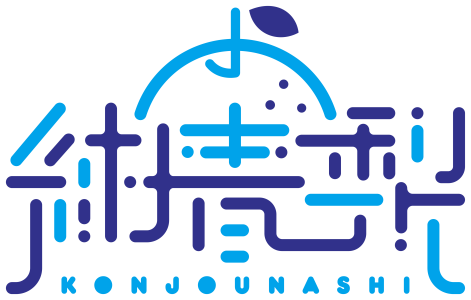「クリス先輩、俺の話を聞いてください」
練習終わりに先輩を引き留めると、この数ヶ月間、三年前のようにひたすらにアプローチした俺に観念したクリス先輩が頷いた。前回と同じ定食屋で食事を詰め込んで、俺の部屋へ向かう。
お邪魔します、と同じようにクリス先輩が玄関を潜った。俺も同じようにお茶を出して、今度は迷う事なくクリス先輩の正面へ座った。
「俺は、いっぱい考えたんですけど、やっぱり勘違いなんかじゃないです」
「…沢村」
俺に伸ばされたクリス先輩の腕を掴む。
「あなたに俺の気持ちを否定されて、すごく辛かった。すぐに声が出せないほどショックでした。あなたには一番知って欲しかったのに、降谷みたいに振られるにしても全部聞く前にあなたは俺の口を塞いだ」
クリス先輩がハッとした。すまない、と俯いて首を振る。そんなつもりじゃなかったんだ、と力なく笑う。
「初めて会った貴方からは森の中にいるような落ち着く匂いがしました。こんなに暗い人なのに何でこんなに落ち着く匂いがするんだろうって不思議でした」
たぶんそれが、クリス先輩の言う初めて嗅いだ同種の落ち着く匂いだったのだと思う。オオカミや犬の混じった斑類は基本的に鼻がいい。だから他の斑類よりずっと色んな匂いで選んでいるのだ。
「初めてクリス先輩が俺に笑いかけてくれた時、花が咲いたと思ったんです。森の匂いに甘くて優しい花の匂いが混じって、この人だ!と思いました」
俯いていたクリス先輩が顔を上げた。
「クリス先輩、俺のパートナーになってください」
「…沢村」
「まだ、勘違いだって言いますか?俺はクリス先輩じゃなきゃ嫌です。貴方が好きだから、貴方ともっと野球がしたかった」
真っ直ぐクリス先輩の目を見つめるとそのまま見つめ返された。じわじわと頬に熱が集まる。向かい合ったクリス先輩の顔も少しずつ赤くなっていく。
「…俺の負けだな」
クリス先輩が笑う。ぶわりと辺り一面を花が埋め尽くしたように甘い匂いが広がった。
「クリス先輩、隣に行ってもいいですか」
「…あぁ、うん。おいで、俺も、お前に触れたい」
堪らず抱き締めて、首筋に鼻を埋めて息を大きく吸い込むとクラクラした。クリス先輩も同じように俺の匂いを嗅いでいる。
「もう、甘い匂いしかしないっす。クリス先輩、おいしそう」
「んっ…」
かぷ、と堪らず首筋に軽く噛みつくと甘い声がクリス先輩の口から溢れた。べりっと音がしそうな勢いで引き剥がされるとクリス先輩が真っ赤になっていた。
「手が早い!」
「す、すいません!あんまり師匠がおいしそうな匂いがしてつい!」
ぼぼぼっと更にクリス先輩が赤くなった。両手で顔を覆うとテーブルに突っ伏してしまった。
「クリス先輩?!」
「…そんなことされたら、本当にもう、お前を離してやれなくなるぞ…」
「まだそんなこと言うんですか!」
「だって、こんなに良い匂いが、他の斑類にも感じ取れないわけがないじゃないか」
混乱しすぎて耳も尻尾も出てしまっているのに、きっとそれにも気付かないほど、クリス先輩は困惑しているのだ。俺に少し手を出されただけでこんなになってしまうのに、この人は大学の残り二年間だけで俺を諦めようとした。
「…先輩、運命の相手以外に、こんな匂いはわからないですよ」
力を込めすぎないように優しく肩を抱き込むように触れるとようやく顔を上げてくれた。チュ、と触れるだけのキスをして顔を離すと泣きそうな顔でクリス先輩が笑う。
「沢村」
「はい」
クリス先輩が俺に腕を伸ばした。抱き寄せられて、唇が重なった。クリス先輩から、キスをされた。
「俺をお前の番いにしてくれ」
「はい、喜んで!」
運命の相手は、蘭の花の香りがすると言う。
斑類の恋は、基本的に一目惚れだ。本能が出会った瞬間この人だと知らせるのだと言う。
俺だってこの人だと思ったことがないわけではないけれど、その人をそんな目で見ていいのか、未だに決心がつかずにいるのは自分らしくないとわかっていたって、俺にだって怖いことだってあるのだ。
「倉持先輩と御幸、センパイは一目惚れ同士なんですか?」
「お前、御幸呼ぶ時だけなんで詰まるんだよ。…悪いかよ、一目惚れで。御幸はどうか知らねえよ」
「まあ、あの人顔だけは良いですからね。本能以外の一目惚れもされてそうっすね」
「まあそうだろうな」
宿題でもやっていたのか机に向かう倉持先輩に問いかけるといつもより柔らかい表情で答えてくれた。御幸先輩のことを考えているせいだろう。わかりやすいチーターだ。
倉持先輩と御幸先輩は、校内の斑類ならみんな知ってるぐらい有名なカップルだ。同じクラス、同じ部活でいつも一緒にいて、よく喧嘩しているけどそれが戯れあいなのは魂現にダダ漏れで仲睦まじいことこの上ない。
そんなことに気がつかない猿人の女子がよく御幸先輩に告白しては玉砕しているのを俺ですら知っている。たまに猿人以外にも告白されたりもしているが、いつも野球以外に使う時間はないから、と断っていることまで知っている。
一度、じゃあなんで倉持先輩と付き合ってるんですか、と問えば、倉持は野球の一部だろ、と不思議そうな顔で返された。これたぶん御幸先輩もあんたに一目惚れで現在進行形でメロメロっすよ、倉持先輩!
それにしても御幸先輩に告白しようと思う斑類は、よくもまあ、あんなにべったりと他の雄の臭いをつけた男が靡くと思うなあと感心してしまう。あからさまに、他人のものですと全裸にマジックで書いて歩いてるようなものだ。
倉持先輩は猫又の中間種、御幸先輩は犬神人の軽種だが、身体は御幸先輩の方が大きいから俺は最初、御幸先輩は重種だと思っていた。青道野球部は斑類が大多数を占めているしレギュラーのスタメンは全員斑類だ。そんな中で一年生から正捕手なんてやっていれば誰だって重種か半重種だろうと思うのに、御幸先輩は軽種のタヌキだった。
雑誌だけを見てこの人なら自分の全力の球を受けられるかも知れないと遥々北海道からやってきた熊樫重種の降谷は、軽種を侮っているわけではないけれどさすがに驚いていた。そして、そのまま御幸先輩に恋をした。まあ顔は整っているので全く気持ちがわからんわけではない。ずっと憧れていた人の実物に会ったらそんな勘違いをしてしまうのもしょうがないかもしれない。
軽種でしかも今のパートナーが中間種なら、より魅力的に見えるはずの重種の自分の子供を産んで欲しいと降谷は御幸先輩に熱烈にアタックしていたが見事に玉砕していた。
相性が悪いのか、重種の降谷のフェロモンが軽種のはずの御幸には一切効かなかったのだ。ブラインドもされていない軽種の犬に自分のフェロモンが効かなかった事に降谷は動揺していた。
倉持先輩は分類上は中間種だが、血縁上の父親が重種のため、この国では半重種と呼ばれる。ブラインドも出来るはずだがその類のものを御幸先輩にかけていない。重種と半重種では例えブラインドをしていても上書きされてしまうかもしれないが、多少の防衛になるはずのそれを倉持先輩は良しとしなかった。
独占欲の強そうな人なのにどうしてしないのだと聞いたら、そんなもので御幸を縛りたくないのだと答えた。
「Hもしてないですよね、先輩たち」
「…この寮の中でどうやって場所と時間確保すんだよ」
お前と降谷がすぐ御幸追っかけてくんだろ、と呆れた声で言う。確かに、言われてみれば降谷はついでに二人の邪魔をしようとしているのかもしれない。
「でも死ぬほど御幸先輩からは倉持先輩の匂いするんだからマーキングはしてるんでしょ?なんでやっちまわないんですか」
まだ完全に御幸先輩は倉持先輩のものじゃない、と降谷が諦めきれない理由がそれなのに、先輩たちは余裕の顔だ。可愛い(であろう)後輩の為にもとっとと行き着くところまで行ってくれればいいのに、と思う。
「そんなことしてあいつのプレーになんか影響あったらそっちの方が耐えきれねえから」
俺も人のことは言えないが清々しいまでの野球馬鹿だ。誰かに横取りされるより、野球に影響が出る方が嫌だなんて徹底している。
「運命の相手は蘭の匂いがするって、本当ですか」
「…それは純さんの読んでる少女漫画の話だろ」
「降谷は何かわからないけど御幸先輩は花の匂いがするって言ってやした!」
御幸先輩の話題の中に降谷の名前を出すとあからさまに嫌そうな顔をするくせに、どうしてはっきりと自分の雌に手を出すなと言わないのか不思議で仕方ない。
「…御幸は、百合の花の匂いがする」
「御幸先輩は、倉持先輩から花の匂いとかしますか?」
「花?かどうかはわかんないけど、なんか甘い良い匂いはするなぁ」
「じゃあ降谷からは?」
「え?何も匂わないけど」
強いて言えばグラウンドの土の匂いと汗の匂い?野球の匂いだなーと能天気に笑っている。
可哀想な降谷である。運命の一目惚れは降谷の一方通行、先輩たちは双方向らしい。明日は投球練習五球ぐらいは譲ってやろう。
それが何?と首を傾げる仕草が野球をしている時のような鋭さがなくフワフワとして不思議な人だと思う。
風呂上りに自販機でジュースを買っていると食堂でスコアブックを見ていたと言う御幸先輩と鉢合わせた。今日は自主練に球受けろって来なかったな、と言われて倉持先輩と話していたことを思い出してベンチに座ると御幸先輩にも聞いてみた。
「運命の相手は、蘭の匂いがするんですって。ちなみに倉持先輩に聞いたら御幸は百合の匂いがするって言ってやした!」
「…なんか恥ずかしいな、それ」
「でも嬉しそうっすね、御幸先輩。本当に倉持先輩が好きなんですね」
「…俺は、一目惚れだったから、運命に従おうって思っただけだけど、こんなに好きになるとも思わなかったなぁ」
いつもはキリッとしている眉を困ったように八の字にしてふにゃりと笑う。普段が少女漫画に出てくる主人公が憧れるイケメンなら、倉持先輩の話をする時の御幸先輩はちょっとドジで可愛い主人公みたいになってしまう。
降谷の話じゃこうはならない。あれは意地悪な幼馴染みとかライバルみたいな顔だ。
「お前は?花の匂いがする人、いるの?」
「師匠が一番良い匂いがするに決まってるじゃないっすか!」
「へー?」
ニヤニヤと御幸が悪い顔で笑っている。何ですか?と首を傾げると御幸先輩が俺の背後を指差した。
「うへぇ?!し、師匠?!どこから聴いてましたか?!」
「…御幸が、百合の花の匂いがするって、ところから…」
振り返ると顔を真っ赤にしたクリス先輩が立っていた。盗み聞きする気はなかったんだ、と謝られて気づいていたのなら言えよ!と御幸に視線を向けると知らない、とばかりに御幸がわざとらしく視線を外した。
その視線の先に誰か見つけたのか、あ、と小さく声を上げ、軽くクリス先輩にだけ頭を下げると嬉しそうな顔をしてそのまま御幸先輩は立ち上がって行ってしまった。小走りに駆け寄った先には倉持先輩がいた。あんまり馬鹿で遊ぶなよ、と叱られている。そーですよ、倉持先輩、もっと言ってやってください!俺のこと馬鹿って呼んだのは許してあげます!
御幸を叱るのは倉持先輩に任せて、まだ顔を赤くしているクリス先輩に向き直る。
「いや、あの、師匠!この不肖沢村、決してそんな倉持先輩が御幸先輩に向けるようないやらしい目で師匠を見たりなんぞは誓ってしてませんからね!」
「…知ってる」
優しい声が笑いを堪えるように震えながら、わしわしと頭を撫でられた。少し呆れたような優しい顔でクリス先輩が笑うと、ふわりと森の中にいるような香りがする。俺は軽種の柴犬の振りをしているが、本当の魂現もそう変わらないから鼻がいい自信はある。瑞々しい木々の匂いに混ざって甘い、花のようないい匂いがする。
「ところでお前は、蘭の香りを知っているのか?」
「…はっ、言われてみれば知らないです!」
クリス先輩が楽しそうにクスクスと笑った。