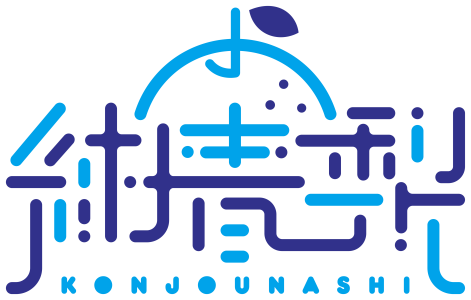2022.12.18発行
A5/32P
書き下ろし分冒頭サンプルです
人生で一度だけ、運命の恋をした。
相手は中間種のチーターで、俺は軽種のタヌキ。重種相手ではないものの十分身分違いの恋だったから、最初から俺と同じ気持ちが返ってくる期待なんてしていなかった。
発情期の思春期パッチでも抑えきれない身体の熱に浮かされて、全部それのせいにして叶わぬ初恋相手に抱いて欲しいと迫った。
同じ部活で同じクラスで同じ寮に住んでいて、一番近くにいることだけは許されているのはわかっていたから、あわよくばその手で触れて欲しくてダメ元の懇願だった。
同じ野球馬鹿として信頼はされていても、自分が好かれているなんて思いもしなかった。お前しかいない、と脅す様にそそのかせば、あっさりとその手は俺の頬を優しく撫でた。触れ合った唇は想像していたよりずっと柔らかくて気持ち良くて、世界で一番今この瞬間の俺が幸せなんじゃないかと思った。
暴力のような交わりで良かった。一方的に俺の身体を使って気持ち良くなってくれれば良かった。あわよくばそれで一度で終わらなければいいな、などと思っていたのに、恋焦がれたその肉刺だらけの掌は俺の性感も高めて、優しく俺を翻弄した。
傷付けないようにと細心の注意を払っているのに、その目はギラギラと、獲物を追い詰める猛獣のように飢えた色を隠しもせずに輝いて見えていた。
初めてで硬く閉ざされた穴をどうにか緩めて解して、その狭い中を硬くて熱い彼のペニスが拡げていく。少しの隙間もなく繋がって、愛おしさが募って仕方なかった。眉間に皺を寄せていた彼がフッと笑って俺に顔を寄せる。お互いに目を瞑らないまま唇を合わせて、吹き出す様に同時に笑いあった。
「痛くねえか、御幸」
「どうしよう、めっちゃ痛えのに、……めちゃくちゃ気持ちいい」
「ヒャハ、マゾかよ」
アザだらけの内股を彼の肉刺だらけの掌が撫でる。慈しむ様な目に心臓が跳ねた。心まで欲しいなんて恐ろしくて言えなくて、身体だけで良かったはずだった。
初めてをどうしても彼で埋めて欲しかった。二度目なんて望むのは贅沢過ぎると思っていた。
それなのに、一度触れ合って仕舞えば、そこからはもうなし崩しに発情期が終わってもどちらかの性欲が溜まれば触れ合って、抱き合って、愛おしいと、毎回セックスの最中の倉持の目が語っていた。好きでいてもいいのだと、許された気がしていた。
セックスの後、最早同級生にも先輩にも監督たちにだってバレていたから、どうしても倉持の匂いで満たされた狭いベッドで一緒に眠りたいとごねれば、いつも最後は仕方ないなと諦めて笑ってくれていた。一度も、好きだとか付き合いたいとか、言葉にするような関係ではなかったけれど、いつも互いにマーキングして、好意はなによりも伝わっていると思っていた。
ふわふわとした心地で顔に似合わず少女漫画が好きな面倒見のいい先輩に惚気れば、良かったな、と頭を撫でられ、倉持の同室の後輩である沢村はたまに妙に気を利かせて二人きりにしてくれた。
他にも部内にカップルはいたけれど、その中でも特に当たり前のようにいつも二人でいられたのに、部活を引退して、二人部屋になって、俺のドラフトが決まると倉持は消灯時間ギリギリまで部屋に戻ってこなくなり、教室でもどこか俺に距離を取るようになった。
もう後少ししかないのに、と俺が焦れば焦るだけ倉持は当たり前にいた俺の隣から逃げていき、遂に俺の退寮の日にも二人きりになることはなかった。
倉持の目が覚めてしまったんだと気付いたのは、青心寮を出て、球団の寮に入った後だった。
倉持は夢から覚めて、自分より大きくて頑丈な男の身体のメスよりも、小さくて可愛くて柔らかくて守ってあげたくなるようなそんな相手が自分にも相応しいと目が覚めたのだろう。
本当はとても優しい男だ。階級も中間種だから、我が物顔の俺さえ隣にいなければ寄ってくるメスも多いだろう。
いつも文句を言いながらも抱き締めるようにして眠ってくれるその優しさが、好きだった。優しい手が、寝たふりをする髪を撫でてくれるのが好きだった。俺に向けられる、優しい瞳が大好きだった。その目が、セックスの時だけはギラギラと盗塁を狙う時のように熱く燃えるのを見ながら突き上げられるのが堪らなかった。
でも全部、それは夢だったのだ。初恋は叶わないのだ、と教えてくれたのは強面だけど面倒見のいい少女漫画が好きな先輩だった。叶うといいな、と共に願ってくれたのに、やはり初恋は最終的には成就しないものだったらしい。
キャンプ地からバタバタと戻った卒業式の日も、倉持は決して俺と二人きりにはなろうとしなかった。沢村と降谷に絡まれながら一度だけ目が合ったのも直ぐに逸らされ、いつの間にか倉持の姿はなかった。
愛おしくなるような幸せな日々の証明は、倉持とのセックスに慣れた俺の身体だけだった。