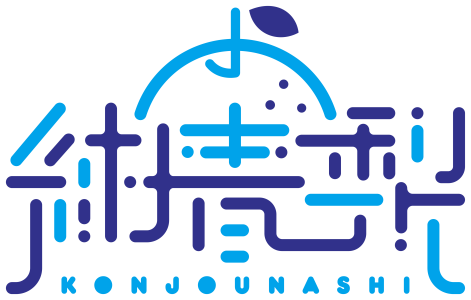2022.07.24発行
A5/64P
書き下ろし分冒頭サンプルです
幼い頃、父親のいない家庭を、未婚のまま俺を産み育てる母を馬鹿にされて、近所の悪ガキと喧嘩をしたことがあった。
子どもながらに、俺の家族は母と祖父と俺の三人きりで、父親の話はしてはいけないと思っていた。
『貴方は、お父さんとお母さんの大事な宝物なのよ』
初めての喧嘩の理由を知った母は、そう言って俺を抱きしめて慰めたけれど、それならば何故父は一度も俺に会いに来ないのだろうとずっと疑っていた。
きっと母は、俺の父に騙されたのだ。騙されて、俺は産まれてしまったから父には望まれても愛されてもいないのに母はいつも俺を大切にしてくれたから、せめてこの人を守る力が欲しいと思った。
その後、たった一度だけ、誘拐されかけた俺を助けに来た父の魂元の姿を見た。大きくて、強くて、優しくて。俺を抱きしめる腕の暖かさと強さに、母の言葉は嘘ではなかったのだと知った。
確かに俺は望まれて、愛されて父と母の子として産まれたのに、守られてばかりの自分が悔しかった。
反抗期にヤンチャをして散々迷惑も心配もかけて、夢すら諦めかけた時にも、母は俺を信じて背中を押してくれた。
いつか、必ず母に恩返しがしたかった。その為にも、せっかく辞めずに済んだ野球に、三年間の全てを注ぎ込もうと思った。憧れはあるが恋なんてきっとしている暇なんてない。
どんなに苦しくても、辛くても、もしかしたら憧れたプロ野球選手にだってなれるかもしれない。
それがどんなに辛く厳しい道でも、今度こそ諦めるつもりは、なかった。
重種はお前だけか、と問い掛ければ、向かいに座って白米が山盛りになった茶碗を手にした御幸は首を傾げた。何とぼけてやがる、と威嚇するとムカつく顔でへら、と笑う。
「俺、軽種のタヌキだよ」
驚きの声とガタガタと動揺して椅子を揺らす音が食堂全体に響く。同学年だけでなく、先輩たちの中にも何人か動揺した人がいるらしい。
練習初日の体力テストで、新一年生の中ではずば抜けた成績で早々にブルペンに入ることを許された一年生捕手がそんなことを言うのだから納得の反応だ。
「倉持くんは足の速さまんまのチーターだから中間種?半重種がいないならお前が一番階級上なんじゃないかな?」
「……一応、親父が重種らしいし、半重種だけど」
「他の中間種も犬ばっかだから猫又の方が上だろ?」
だからいい匂いすんのかー、と御幸が笑う。普通の軽種は俺が半重種だとわかると怯えるか媚を売るが、御幸はどうやら相当に肝の座った軽種らしい。
未だにヤンキー臭さが滲み出てしまっているのか、気の弱そうな真面目そうな同輩にはまだ少し怖がられているような気がしている。
「軽種らしくないやっちゃなぁ、御幸は」
「前園くんは土佐犬?」
「マナー違反や、アホ」
ぺしり、と隣に座っていた前園に軽く叩かれて御幸がいてっ、と反応した。実際はそんなに痛くもなさそうだった。
「……俺、タヌキだって言ったじゃん」
「お前が勝手に言うただけやろ。人の魂元勝手にバラすのはあかん」
「……お前、ランニングの最後の方で魂元出てたけどな」
「……気ぃ付けるわ……」
威勢のいい前園が、俺の指摘にシュンとした。その隙に御幸がひょい、とおかずを一口分前園の皿へ移す。お前、と声を掛けようとすればシーッと口の前に指を立てた。前園は全く気付かないまま食事を再開した。
「さすがにそんな重種ばっかりいないって。稲実は猫又最重種も入ったし多いらしいけど」
「ふーん」
同じ地区の別の野球の名門校の名前に、興味がないと言えば嘘になるが、今はライバル校よりまずは青道の中で一軍に、レギュラーにならなければ話にならない。
小柄だが気の強くて技術のある二塁手の先輩に、俺は毎日クタクタになるまで嫌味を言われながらシゴかれている。まずはあの人に追いついて食らい付かなくてはいけないのだ。
「何や、御幸。稲実からもスカウト来とったんか、お前」
「うん。でも重種ばっかだったから、青道にした」
練習中はいい性格してやがる、と思ったが、前園との会話を聞いていると素直に答えるのが少し意外だった。
「は?何でや?」
「だって、青道にはあの人がいるから……」
御幸が、チラッと二年生のグループを見る。その視線の先を追えば、青道の正捕手がいた。
「滝川先輩か。お前、下手したら二年の秋まで控え捕手になんのにか?ええ度胸しとるのぉ」
「稲実にも正捕手はいるし、だったら俺は滝川さんと正捕手争いしたくて来たの!稲実よりずっと前から礼ちゃんは声かけてくれてたし」
「……お前、副部長とどう言う関係だよ?」
少し気になっていたことを問いかけてみると、きょとん、と御幸がまた子どもっぽい表情で首を傾げた。御幸は妙に気安く、あの副部長に話しかけ、副部長もそれを邪険にするでもなく、むしろ可愛がっているように見えた。
「へ?……うーん、中一の俺をスカウトしちゃう、ちょっとおっちょこちょいな可愛いお姉さん?礼ちゃんも俺のこと弟ぐらいにしか思ってないよ」
「いや、そうじゃねえよ」
「声かけてくれた時、まだ先生じゃなくてさぁ、それからずっと礼ちゃんって呼んでるから学校では気を付けてんだけど、一応」
どうやら御幸は色々規格外らしい。確かに学校では天才捕手と呼ばれるあの完璧さは形を潜め、廊下を歩けば何もないところで躓き、階段は踏み外しそうになり、体育の授業では鈍臭さを遺憾なく発揮していた。
整った容姿に女子は沸いていたが野暮ったい黒縁メガネに顔を隠すような前髪は少しだけ勿体無いとも思う。本人は全く自分の容姿には興味はないようだ。
「設備も、稲実の方が確かに最新の設備もあったけど、ウチだって負けてなかったし、それに、あんなに重種ばっかり集まったチーム、倒す方が面白いだろ?」
にしし、と笑う。心底ここでの野球が楽しい、と言う顔で笑う御幸が、何故だかキラキラと輝いて見えた。